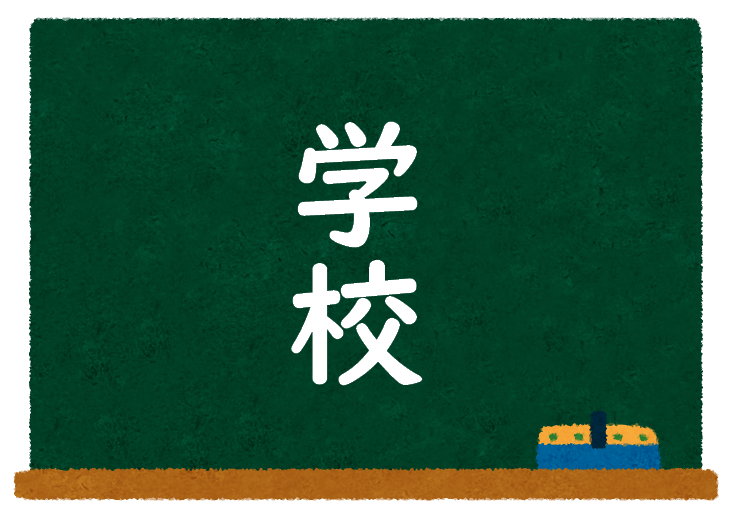作品概要
映画『学校』は1993年11月6日の公開。後に第4作まで作られることになるシリーズの第1作目。
なんらかの事情で中学校を卒業できなかった人たちを受け入れている夜間中学を舞台に、年齢も経歴も人種すらも異なる生徒たちと体当たりで接する教師たちとの心の通った「師弟関係」を描いています。
就学年齢というだけで集められ、画一的で息苦しい「教育」を与えられる昼間の学校との違いを浮き彫りにすることで、勉強することにどんな意味があるのか、と観ている者にも問いかけます。
松竹創業100周年記念作品。日本テレビ放送網開局40年記念作品。芸術文化振興基金助成作品。文部省特選。
主なキャスト
- クロちゃん(黒井)先生:西田敏行
- 田島先生:竹下景子
- イノさん:田中邦衛
- カズ:萩原聖人
- えり子:中江有里
- オモニ:新屋英子
- 張(チャン):翁華栄
- 修(おさむ):神戸浩
- みどり:裕木奈江
- 河合医師:大江千里
山田洋次監督が映画『学校』を撮るまで
山田洋次監督は映画『学校』シリーズを撮るきっかけとなった経験を、『「学校」が教えてくれたこと』(PHP研究所)という一冊の本にしています。
山田監督が夜間中学の存在を知ったのは1970年代のこと。知り合いの脚本家から「夜間中学というところがあるから、一度一緒に行ってみないか」と誘われたのがきっかけでした。
しかし監督は、夜間中学が映画のテーマになるとは考えなかったそうです。暗い教室で仕事に疲れた人たちが勉強をしている、そんな光景が人を楽しませる映画になるとは思えなかったといいます。
教師と生徒とのライブな授業が映画『学校』を生んだ
山田監督が夜間中学の取材を続けていたある日、日本国憲法についての授業が行われました。
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この中で先生は「幸福追求」という言葉に違和感を感じます。
「幸福追求とは、いったいなんのことだ?」
先生は生徒たちに「幸福ってなんだろう?」と問いかけます。50代の男性は家も持てたし家族も元気だから幸福だと言います。しかし、ふだんは大人しい20歳くらいの女性は「おカネじゃないの?」とぶっきらぼうに答えました。
先生は我が意を得たりといった感じで、「そうだよ! みんなもカッコいいこと言わずに正直に言えよ」と生徒たちをけしかけます。さらに先生は、幸福にはおカネさえあればいいのか、と踏み込んだ質問を生徒たちに投げかけます。
そうした先生と生徒たちの生々しいやり取りを見ているうち、山田監督はスクリーンを見ている観客も生徒の一員になってしまうような、映画館が教室になってしまうような作品ができたら素晴らしいだろうな、と思ったのが映画『学校』を撮るきっかけとなったそうです。
このシーンは今作の中でもクライマックスとして取り入れられています。
クロちゃん先生に故郷で療養中だったイノさんが亡くなったと知らせが入ります。急遽行われたホームルームで訃報を知らされたカズは、働きづめで死んだイノさんの人生は不幸だと嘆きます。そこでクロちゃん先生は「幸福とはなんだろう?」と生徒たちに問いかけます。
焼き肉店を経営する朝鮮人女性のオモニは、自分が幸せだと思ってさえいれば幸せだと言います。その言葉にクラスメートたちは、幸せはただの錯覚なのかと異論を唱えます。こうしてホームルームは「幸福」について生徒たちのあいだで喧々諤々のディスカッションとなります。
このシーンでは、みどり役の裕木奈江の演技が見事でした。不良少女役の彼女がこれまでの悲惨な生き方を告白し、クロちゃん先生に声をかけられて夜間中学に入れることになったとき、「これでワタシ、幸せになれるかもしれないと思った」と泣きながら話すシーンは彼女の女優としての力量を見せてくれます。
映画『学校』ができるまでの15年間の歳月
山田監督が映画『学校』を撮るまでには、15年ほどの時間がかかっています。松竹の屋台骨を支える監督は『男はつらいよ』シリーズや『幸福の黄色いハンカチ』など数々の作品を撮っていて多忙を極めていたためでした。
そんな中でも、夜間学校を舞台にした作品が一本あります。1980年12月に公開された『男はつらいよ 寅次郎かもめ歌』という「寅さんシリーズ」の26作目です。
僕はこの頃から『学校』という映画を作りたいと思っていました。
(中略)
この作品のマドンナ役の“すみれ”という娘が伊藤蘭さん。題材は地味でしたが、この作品は興行成績がとてもよかったのです。
そして僕はこのとき、日本人が教育という問題にどれだけ悩んでいるのかということを感じました。
「男はつらいよ 寅さん読本」PHP文庫
この作品は寅さんが亡くなったテキヤ仲間の娘(伊藤蘭)を北海道から東京に連れ帰り、定時制高校に通わせる話です 。国語教師役の松村達雄と渥美清の息の合った演技が夜の教室を楽しくさせる、シリーズ50作の中でも名作と言える作品です。
舞台は夜間中学ではなく定時制高校ですが、これが映画『学校』につながる試作的な作品になったのは明らかです。
この作品では国語の授業で濱口國雄の「便所掃除」という詩が取り上げられていますが、映画『学校』でも大関松三郎の『夕日』という詩が取り上げられています。
どちらの詩にも共通するのは、地道に働く労働者の暮らし。
「便所掃除」はまだ汲み取り式だったトイレ掃除の苦労が若い旧国鉄職員の素朴な筆致で語られ、「夕日」では畑仕事に疲れて帰る農民の苦労が豊かな情景で語られています。
「左寄り」の山田監督がいかにも好みそうなテーマですが、それでも当時の労働者には明日への希望があった時代だったと思えます。それに比べて今はといえば、もう日本という国に絶望しか感じない人も多いんじゃないでしょうか?
大人でも字が書けない人がいた時代
今作には50代になっても字が書けないイノさんやオモニが出てきますが、今の時代ではそんな人がいたなんて信じられないかもしれません。しかし、ぼくにも一度だけそんな人がいるんだと思った出来事があります。
時代はバブル景気の直前、1985年(昭和60年)のことです。そのころぼくは地元の教習所に通っていました。
ある日、教習所の職員たちが道路交通法のテキストに「ひらがな」をふっています。訊くと、漢字を読めない人が自動車免許を取りに来ているので、テキストの漢字すべてに「かな」をふっていると言っていました。
今作でもリアカーを引いて重い荷物を運ぶイノさんにとって、運転ができるようになることは夢でした。あの教習所に通っていた漢字の読めない人も、自動車免許さえあれば、きっと生きるのがラクになると思っていたんでしょうね。
しかし、こういう悲哀に満ちた男を演じさせたら田中邦衛の右に出る者はいません。というか、田中邦衛さえ出せば、もうそれだけで納得しちゃうじゃないですか。ある意味「反則」と言ってもいいくらいのキャスティングです。
そしてイノさんが好きな田島先生役は「お嫁さんにしたい女優No.1」だった竹下景子。この二人はドラマ『北の国から』でも義兄妹で共演した仲でしたが、竹下景子は『男はつらいよ』シリーズにも3度マドンナ役で出演しているほど山田監督お気に入りの女優さんでした。
いい加減に時代遅れの教育制度を改めては?
ぼくが中学生だったのは昭和50年代。当時は管理教育の全盛期で、教師たちは独裁者のように振る舞っていました。
気分次第で生徒を殴ることなどあたりまえ。少しでも反抗的な生徒に対しては、徹底的に差別と嫌味を繰り返す人間のクズのような教師たちがウヨウヨしていた学校でした。
そんな中学生活に辟易していたぼくは、終礼と共にさっさと帰宅する生徒でした。おとなになってから「おまえは終礼の直後に、もう学校の外を歩いていた」と言われたくらいで、「よっぽど学校が嫌いなんだな」と思われていたそうです。
しかし昔の教師たちの傍若無人な態度は、ある意味あたりまえだったかもしれません。なぜなら、日本の学校は従順な労働力を生産する工場だからです。
今のような学校制度が始まったのは明治になってから。その頃の日本は「富国強兵」に励んでいた時代です。そのためには最低限の読み書きができて、上からの命令に従う扱いやすい「羊たち」を量産することが「教育」の目的でした。それが今でも続く「義務教育」の始まりです。
だから当時の教師たちの振る舞いは、明治時代から続く学校の目的を考えると当然だったとも言えます。しかし、そんな「教育」がこれからの時代に通用するでしょうか?
「一寸先は闇」のこの時代に「右へ倣え」「命令遵守」の教育を続けていくことは、この国にとって百害あって一利なしです。
学校という閉鎖的な空間がブラック化して「いじめ」という犯罪が蔓延しているような状態で、これ以上、旧態依然の義務教育を続けていく必要があるんでしょうか?
じっさいの夜間中学では、生徒一人ひとりにあわせたテキストを用意して教えていたそうです。教師にとっては手間がかかってたいへんでしょうが、生きるために必要なことをしっかり身につけさせる江戸時代の寺子屋や私塾のような教え方ですね。
ムダな知識の詰め込みや、理解できなくても学校に来なくても、時期がくれば強制的に「卒業」させるやり方は意味を失っているとしか思えません。
映画『学校』シリーズを観ると、いかに今の学校が問題だらけの空間に堕しているかと痛感します。